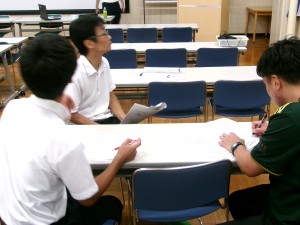すべての著作権は当岸和田市教育センターにあります。住所 岸和田市天神山町1-1-2 電話 072-426-1001
岸和田市教育センター
研修記事(~R7.9月)
8月4日(月)14時より、「令和7年度 管理職研修(教頭・主任)」を実施しました。
株式会社RESQOM 代表取締役 次田 昌弘 様を講師にお招きし、『職員一人ひとりの「モチベーション」を高め、働きやすい職場を作るためのポイント〜今、私たちに何ができるのか〜』をテーマに研修を行いました。
モチベーションとはどのようなものであるか、また自分のモチベーションが向上するときはどのようなときであるかなどをペア等で共有しながら確認しました。また、言語以外の非言語コミュニケーション(表情・態度やしぐさなど)が話しやすい環境づくりにとても大きな影響を与えていることなども具体例を通して学びました。
日常的にどのような言葉かけや姿勢が求められるか、ワークショップを交えながら学びました。
成果だけでなく、過程に注目し、個々の成長を促すような適切なフィードバックや評価が、教職員のモチベーションを高める鍵であることを再確認しました。
学校を支える中核的な立場として、日々の関わり方を見直し、より良い組織づくりを考える機会となりました。
【先生方のアンケートより(一部抜粋)】
・コミュニケーションの具体的な話が聞けてよかった。働きやすく・働きがいのある職場づくりに努めたいと思った。
・自分が正しいのではなく、相手がどのように思っているか・どう見ているかということを考えながらコミュニケーションをとっていきたいと思った。
・モチベーションを高めるポイントを再確認できた。ほめ言葉を複数パターンもち、フィードバックを心がけていこうと思う。
・改めて自分のモチベーションについて気づくことができ、安定させられるように努めたい。
・コミュニケーションの大切さ、聴く姿勢・環境づくりの大切さを再認識し、今の自分を振り返ることができた。
8月5日(火)10時より、「令和7年度 小中学校社会科研修」を実施しました。
岸和田市議会事務局 柴田 倫子様を講師としてお招きし、市議会や市政のしくみ、市議会議員の仕事などについてわかりやすく解説していただきました。
前半は、地方自治が憲法や法令に基づいて行われていることや、市民の声をどのように市政に反映させているのか、市議会の役割、市議会議員が日頃どのような活動をしているのかについて、具体例を交えながら学ぶことができました。
また、後半には模擬議会を体験しました。議長役や市長役に分かれ、ある議題について討論・採決を行いました。実際の議会さながらの雰囲気の中で、地方政治の大切さや議論の難しさを実感する貴重な機会となりました。
【先生方のアンケートより(一部抜粋)】
・百条委員会のしくみなど、ニュースでもよく聞くことなので、興味を持って聞くことができ勉強になった。
・議会がきちんと運営されるための事務方の仕事量がとても多いと推測できました。
・小学校の社会科の単元へのつなげ方などがあれば知りたいと思った。
・模擬議会の台本を使って、授業でもやってみたいと思った。表現が難しいところがあるので、生徒が身近に感じられるような工夫があれば、もっと市政が広がると思った。
・社会科で学習したことが実際に執り行われているので、ぜひ子どもたちにも体験させたいと感じた。
8月6日(水)13時より、「令和7年度 中学校技術科研修」を実施しました。
葛城書店の職員の方をお招きして、教材の紹介をしていただきました。「ダイナモラジオ‘フレア’」を使って、実際に作業しながら、教材研究を行いました。
8月6日(水)15時より、『令和7年度 「総合的な学習の時間」研修』を実施しました。
大阪教育大学 准教授 佐久間 敦史 様をお招きし、小中学校の先生方を対象として、探求的な学びのあり方や市内・他市の実践例、これからの教育に求められる視点についてご講演いただきました。
研修では、子どもたちの「やってみたい!」という気持ちから始まる学びの芽をどのように育てていくか、就学前の学びと中学校と連携した小学校の取組みを紹介していただきました。学びの連続性を意識した内容に、多くの先生方が関心を寄せていました。また、地域と連携した実践例では、今後の取組みのヒントになる内容をたくさん紹介していただきました。
さらに、「公正に個別最適な学び」を実現するために、「教師の役割について」や「環境整備について」、「子どもたちの多様な学び方に対しての支援方法について」も教えていただき、多くの学びがありました。
【先生方のアンケートより(一部抜粋)】
・課題(もやもや)をどうすればよいのか、身近なことから取り組めると思った。
・子どもたちの「やってみたい」を「そんなことできない」とつぶしてしまわないように、また、子どもたちが「どうせできないやろ」と思わせないように成功体験を積み重ねていきたいと思った。
・教師の役割はファシリテーターであるというのが、すごく心に残った。子どもたちの「調べたい」「知りたい」をサポートできるような授業づくりを考えていきたい。
・授業の見直しを行う必要があると とても感じた。教師の意識をアップデートする方法を考えることが必要だと思った。
8月8日(金)10時より、「令和7年度 市実施小中学校初任者研修②・講師研修②(人権教育研修)」を実施しました。
小中学校の初任者・新規採用者、講師の先生方を対象に、人権教育課の関根指導主事と南指導主事が研修を行いました。
研修では、子どもたちの身近にあるさまざまな人権課題について取り上げ、「人権に関する知識・理解を深めること」の重要性や日々の教育実践でどのような意識が必要であるかについて、参加者で話し合いました。
「教科指導」「生徒指導」「キャリア・進路指導」等全ての教育活動において、人権尊重の考え方が根底にあることや、日ごろの取組みとのつながりを意識することで人権教育が深まっていくことを確認しました。
特別支援教育については、支援を考える4つのステップ(①気づく②見直す③支援する④つなぐ)の内容を取り上げ、それぞれのステップで大切な視点や具体的な支援方法について確認しました。
【先生方のアンケートより(一部抜粋)】
・知らず知らずのうちに子どもたちを傷つけてしまっている「かもしれない」というアンテナを常にはっておこうと思った。
・日ごろ行っていたこと全てが人権教育・平和教育につながっていることが分かったので、今後はより意識して学級運営や指導に向き合っていきたい。
・人権課題について知るだけでなく、知ったうえで認め合い尊重し合える集団になれるよう働きかけをしていくことが大切だと感じた。
・多様性という言葉が当たり前に使われるようになった今だからこそ、人権についてもう一度考え、取り組んでいく必要があると思う。
8月8日(金)14時より、「令和7年度 市実施小中学校2年目研修②」を実施しました。
小中学校の2年目の先生方を対象に、大きく3つの内容で研修を行いました。
「①幼児教育」は学校教育課 堀端 指導主事、「②不登校対応」は学校教育課 髙橋 指導主事と教育相談室 中津 主任、「③自身の目標設定」は学校教育課 新谷 指導主事が担当しました。
①では、就学前の遊びを通した学びが学校教育にどのようにつながっているのかを確認しました。「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」については、子どもの姿を例に挙げ、教師の見取りや言葉かけ、環境の工夫などを具体的に知ることができました。
②では、不登校に関する法令や調査結果の分析、岸和田市の子どもサポートルーム(エスパル)などについて確認をしました。事例検討では、考えたことをペアやグループで共有しました。これまでの経験や校内での取組みを生かして、活発に意見交流が行われていました。他の人の考えやアイデアを聞き、メモをする姿が多く見られました。
③では、5月に設定した今年度の目標について、1学期の成果と課題、2学期の目標や取組みなどを確認しました。グループで交流することで、校種や学年・担当による違いに触れたり、同じような悩みを抱えていることが分かったりするなど、新たな視点や取組みのアイデアを得る時間となりました。
【先生方のアンケートより(一部抜粋)】
・幼児教育でも、自立心・協調性など細かなところまで考えて園児と接していることを知れた。幼児教育から小学校教育へ接続する際に中1ギャップのようなことがあるのか気になった。
・園児は、遊びの中で様々な学びを得ていることが分かった。大人が想像もできないような考えをもっているなと改めて感じた。
・本人や保護者の思い、チームで対応することが大切だと学んだ。居場所づくりや安心して通える学級をめざして、日々子どもたちと過ごしたいと思った。
・些細なことでも共有しておくことが必要であると思った。また、一人で対応するのではなく、小学校やSC、関係機関と連携し、学校として対応していきたい。
・目標に向けた取り組みを聞けたことがよかった。同じ悩みを抱え、考えて取り組んでいることを知った。
・色々な先生方の1学期の自己評価と2学期の目標を聞く中で、1学期にたくさんの経験をされていることを知り、自分も2学期頑張らないといけないと思った。
8月21日(木)15時30分より、「コグトレ研修」を実施しました。幼稚園と小学校の先生方を対象に、コグトレ学会理事(和泉市立国府小学校 講師)の井阪 幸恵 先生をお迎えし、研修を行いました。
前半は、『先生も「改めて」コグトレをやってみよう!』をテーマに、実際に様々なトレーニングを体験しました。それらの取組みが子どもたちのどのような力につながっているのかを学ぶことができました。
後半は、校種で分かれ、別々のテーマで実施しました。幼稚園は「コグトレから子どもの成長を見とる」をテーマに、実際の子どもたちのアセスメントシートから子どもの成長や課題を読み取ったり、多くの実践例を紹介していただいたりしました。小学校は東京書籍株式会社の担当者様より「コグトレオンライン(コグトレミッション)」について、様々な機能を紹介していただきました。
【先生方のアンケートより(一部抜粋)】
・取り組ませるだけになっているときもあるので、「どうやってしたの?」などと子どもたちどうしで伝え合う時間を作ろうと思った。
・「コグトレミッション」について初めて知った。子どもに実施させる場合は、安心して取り組めるような言葉がけが大切だと思った。
・継ぎ足歩行で姿勢保持ができることを学んだので、日々の保育に取り入れていきたい。
・子どもたちの体幹維持、筋肉調整のため、もっと体を動かせて遊ばせる大切さを痛感した。
8月29日(金)18時15分より、『第3回i-station学習会「COCOLOプランから学ぶ不登校対応~実践編~」』を実施しました。学校教育課 髙橋指導主事と教育相談室 中津主任が担当しました。
前半は、大阪府や岸和田市における不登校支援の施策や「COCOLOプラン」の内容を確認しました。特に、「COCOLOプラン」の3つの基本理念や不登校経験者へのアンケート結果をもとに、対応のポイントを整理しました。
後半は、事例を用いた検討を行いました。提示された情報をもとに個人でアセスメントを行い、その後グループで意見交流をしました。異なる視点に触れることで、自身の考えが深まり、対応の幅が広がるなど、有意義な時間となりました。
【先生方のアンケートより(一部抜粋)】
・事実を書き出してアセスメントを考えたことがなかったが、すごくはっきりわかって、良い方法だと思った。
・当たり前にしていることを継続していくことが大切だとあらためて感じた。
・アセスメントを一人で考えるより、複数で考えると多様な考えが出るので、ケース会議は意味のあるものだと思った。
・アセスメントの重要性は日々感じているので、事例のアセスメント(練習)ができてとても有意義だった。
・登校できなくても、子ども自身が考えて進もうとする気持ちを大切に、これからもサポートしていこうと思った。
9月25日(木)18時15分より、『第4回i-station学習会「体育の授業づくりのポイント~悩める場面を乗り越えるヒント~」』を実施しました。学校教育課 岩城指導主事が担当しました。
前半は、授業づくりのポイントについて考えました。子どものつまずきやすいところや課題設定、時間配分など、子どもたちのやる気を持続させるために必要なことを確認しました。
また、「どのような運動で」「どのようにして」「どのような力をつけるか」という教師のねらいを明確することの大切さについても確認しました。
後半は、実際に体を動かしながら、体つくり運動やネット型ボール運動などの教材について、導入の工夫や運動量を確保するためのアイデアを出し合いました。基礎的な動きにひと工夫加えることで、子どもたちの意欲を維持しながら、技術の向上も図れることが分かりました。